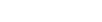湿り気を帯びたぬるい風に吹かれながら、レンタルした自転車をこいでいた。隅田川沿いを北上し、川を越えて浅草へ。
7月5日に日本は滅亡しなかったが、世界が混沌を極めているのを肌で感じる、そんな昼下がり。
浅草といえば芸能文化で栄えた街である。日曜の夜8時にテレビのチャンネルをNHKに合わせれば、その様子の一端を垣間見ることができるだろう。コロナ禍で閑散としていた時期もあったが、いまではすっかり活気を取り戻した。外国人観光客がひしめき合い、芸事を堪能する場の呼び込みよりも、飲み屋の呼び込みのほうがにぎわっている。それはまあ、当然と言えば当然か。
煮込みの匂いに吸い寄せられそうになるが、気を確かに持ってホッピー通りを抜ける。するとしだいに目的地が見えてくる。そう、浅草九劇だ。
金子鈴幸が自身の所属するコンプソンズを飛び出して作・演出を手がけると知ったとき、それはもう胸が高鳴ったものである。1990年生まれの私にとって同世代の彼は特別な劇作家であり演出家だ。
同時代を生きる彼が何をモチーフにして物語を描き、いまの社会とどのように接続させてみせるのか。そしてその物語が繰り広げられる過程で、いったいどんなテーマが浮かび上がってくるのか。
コンプソンズが演劇によって仕掛ける試みは、多くの観客を無傷のまま帰らせてはくれない。劇場空間で立ち上がるナンセンスな笑いに満ちた壮大な(?)フィクションには、私たちの生きる馬鹿げた冗談みたいな現実が反映されている。痛快な物語からその現実がぬっと顔をのぞかせ、目が合ったとき、客席に座る私たち一人ひとりに変化が起こる。
コンプソンズから飛び出した金子は、浅草で何をしようと目論んでいるのか。稽古場に潜入し、金子への取材を試みた。

・とある喫茶店、芸能界──かき集めた素材(=モチーフ)
“推しの子に続く(?)芸能界サスペンスコメディ!”と銘打たれた『きみは一生だれかのバーター』は、地下鉄の駅構内にある「こんにゃく庵」という喫茶店を舞台に物語が展開していく。ここは知る人ぞ知る芸能関係者の憩いの場。ドラマやバラエティの収録スタジオに通ずる特別な喫茶店でもある。そんなこの店にはモデルがあるらしい。
「劇中に『業界の方? 一般の方?』というセリフがあるのですが、これは僕が実際にマスターからかけられた言葉なんですよ。当然ながら僕は友人たちと“一般人”として席に案内してもらったわけですが、別の席には超人気のモデルが座っていました。不思議な空間でしたね。あのときの体験が自分の中でずっと引っかかっていて、今回の物語の舞台にしてみました。僕よりも上の世代の方々の中には、すぐに気がつく人がいると思います」
この不思議な喫茶店を舞台に、さまざまな人間ドラマが展開し、思いがけぬところへと観客を導いていく。
どのように物語を膨らませていったのだろうか。
「素材をかき集められるだけかき集めて、使えそうなものを半ば強引に繋ぎ合わせている感じですかね。“本番”という大いなる締め切りに向かって。今回は多彩なキャストのみなさんに集まっていただいたので、みなさん一人ひとりから得たイメージを膨らませているところもありますし、僕自身が日常的に接している社会の事象や、吸収しているカルチャーを組み合わせていたりもします。
それから指摘されて気がついたのですが、唐十郎の『少女仮面』を想起させるみたいで。読み返してみたら、たしかにそのとおりでした。
『少女仮面』は“肉体”という名前の喫茶店が舞台なんですよ。それも地下にある。
まったく意識していませんでしたが、やっぱりこうやって自分の中に蓄積してきたものが、創作の過程で顕在化してくるものなんですね。
かき集めて繋ぎ合わせる創作スタイルは、コンプソンズで脚本を書くときの取り組み方と同じです。ただ、実際に稽古をしてみて、これまでとの違いを感じています。これを言葉にするならば、“お芝居の力を信じる”みたいなことなのかもしれません。笑えるネタをこれでもかと仕掛けたり、ノリや勢いでシーンを立ち上げるのではなく、お芝居の力で勝負する。みたいな」
金子のこの発言に頷いた。コンプソンズの作品では矢継ぎ早に繰り出される(時事)ネタや、ノリと勢いなどの力技によって立ち上がるシーンを目の前にし、呆気に取られることもしばしば。しかしこれこそが劇団の持ち味でもあり、そこには中毒性もある。
ところが今作の稽古場で私が立ち会ったシーンには、ある種のしっとりとした芝居があった。もちろん、ネタはふんだんに散りばめられているし、ノリも勢いもある。笑うのを我慢できない瞬間も多々ある。
だが、コンプソンズの作品とは印象が異なるのだ。金子の感覚的には「スローペース」なのだという。
「このペースで大丈夫なのかなとも思うんです。僕の感覚的には。でも稽古をやってみて、じっくりと観られるものになっている手応えもありますね。
これに関しては、この作品の企画者である尾上寛之さんとプロデューサーの藤本さんの存在が大きい気がしています。二人はヒトハダという劇団をやっているのですが、ヒトハダはまさに“ザ・芝居”みたいな作品を上演するんですよ。
個人的にすごく好きな劇団ですし、お二人とやるうえで僕自身のモードが自然と変わったのかなと。
関係する人が変われば自然と作風にも影響が生まれるものなのだと実感しています」

・“自分は自分でしかない”という主題
そもそもこの企画は、藤本が金子に声をかけたことによって始まった。
金子はコンプソンズの公演として、2022年11月に『われらの狂気を生き延びる道を教えてください』を浅草九劇で上演。抱腹絶倒のかなりの問題作だったと記憶している。これが二人の出会いの機会となった。
そして、同世代の演劇人と組んで作品づくりをしたいと考えていた藤本は、その相手として金子に声をかけたのだ。若手世代の演劇人と組むことを望んでいた尾上も参画。
こうして『きみは一生だれかのバーター』の企画が本格的に始動した。
芸能人・真島香菜(小西桜子)を中心に、マネージャーの竜禅寺ショウ(尾上寛之)、「こんにゃく庵」の店主・福本ひろし(駒木根隆介)、店にクレームをつける一般人(東野良平)、香菜の高校の担任だった安西先生(山崎静代)、そして、香菜の高校時代の同級生であり、いまは「こんにゃく庵」でアルバイトをしている堂島聖子(井上向日葵)らによって物語が繰り広げられていく。
そのベースにあるのは、“女子同士の関係性に生じる特有の感じ”なのだという。
これは女子高出身者である藤本との会話の中から金子がキャッチしたアイデアだ。
ここであまり深く言及するのはやめておこう。では、今作が手を伸ばそうとしている主題に関してどうなのだろうか。
「この物語は、途中で大きく飛躍します。問題はそれがどこに着地するのかですよね。執筆と稽古を並行しながら見えてきた主題は、“自分は自分でしかない”みたいなことなのかなと。
この“自分は自分でしかない”というのは、要は、この肉体を持っているのが自分である、ということです。
人間は日々の中で変化します。細胞はものすごいスピードで入れ替わるし、環境や人生経験によって考え方だって変わる。じゃあ何をもってして、僕らは“自分”というものを定義づけているのでしょうね。
そこで気がついたのが、ここに触れられる肉体が存在していること。これこそが自分が存在している証なんじゃないかということです。
だから、『我思う、故に我あり』ではなく、『我このイスに座る、故に我あり』みたいな。あるいは、『我話している、故に我あり』とか。つまり、自分の存在を事象として捉えるということです。
どこまで近づけるか分かりませんが、今作の主題でいうと、こういうところかなと。
人間は年齢を重ねて成長し、変化していきます。でも、いくら考え方をアップデートできたところで、過去は変わらない。その人の持つ肉体が変わらないように。
『アップデートしましたよ、私』みたいな人間に対して嫌らしさを覚えるいっぽうで、どうにか肯定していきたい気持ちが僕にはあるんです」

・金子鈴幸のスタンダードナンバーに
多様な言語が飛び交う浅草に、多彩な演技者が集う。
金子は作・演出にできるだけ専念し、キャスティングなどに関しては純粋にプロデュースされる立場を選んだのだという(とはいえ、彼も重要な役どころで出演する)。
キャストから物語のイメージが膨らんでいったように、金子自身も想像していなかった扉を開けることになったのではないだろうか。
「東野さん以外のみなさんは、はじめましてです。藤本さんの案に乗っかりましたね。コンプソンズの公演ではご縁のなかった方々に出てもらわないと、プロデュース公演の意味があまりないと思ったんです。
でもそのいっぽうで、一人くらいは過去にご一緒したことのある、安心できる方にいてほしい思いがありました。そのことをそれとなく伝えたところ、東野さんのキャスティングをご提案いただいたんです。
すごい座組になりましたね。キャスティング段階で提示したプロットの原形は、ほぼほぼ残っていないんですけどね……。オファーを受けてくださったみなさんに本当に感謝しています。
主人公の真島香菜の設定は、完全に小西さんの存在ありきです。三池崇史監督の『初恋』で彼女のことを知りました。作品がめちゃくちゃ面白かったこともあって、特別な存在なんですよね。
小西さんとは年齢的には少し離れていますが、好んで触れてきたものが近いみたいで。香菜のキャラクターには割とそのまま僕自身を投影しています」
“投影”という言葉は稽古中にも出た。金子自身を投影するキャラクターが女性なのか男性なのかで違いや変化はあるのだろうか。
「かなり違いますね。2024年の10月に上演した『ビッグ虚無』は物語の中心に立つのが僕と同じ男性で、書いているうちに嫌になっちゃって。なんだかこう、気分が悪くなってくるというか、落ち込んじゃうというか。男性が男性のことを考えると、どうしても袋小路に入っちゃうんだと実感しました。『所詮は男なんて……』みたいな。
いっぽうで女性のキャラクターだと、どれだけ想像力を働かせても想像しきれないんですよね。どう頑張っても埋まらない部分があるんです。だからもっともっと想像するしかないし、希望を持って書くことができる。
想像力を働かせることって、希望に繋がるんだと僕は捉えています。僕の場合、男性のことを書くと絶望的にしかなりません」
金子の作品が浅草九劇で上演されるのは、これで2度目だ。そこに関して何か特別な思いはあるのか。
「浅草は芸能の街だからか、どことなく泥臭い作品が立ち上がってきています。華やかさの裏には泥臭さがありますからね。少なからず土地の力が作品に影響していると思います。
僕の個人的なテーマとしては、2022年に浅草でやったことをブラッシュアップして、アップデートさせたい気持ちがあります。
そういう意味では、いいとこ取りのベストアルバム的なものになるのかな……集大成?……いや、スタンダードナンバーかもしれません。これが劇作家として、演出家としての新たな基準になるのかなと。それも、高いアベレージの。
これまでの僕の作品からコンプソンズらしさを削ぎ落としたものになるはずなので、金子鈴幸の作品といえば『きみは一生だれかのバーター』になるんじゃないかと思います」
金子鈴幸のスタンダードナンバーとは、果たしてどのようなものになるのか。
混沌としたフィクション作品が立ち上がることになるはずだが、それは私たちの混沌としたリアルを反映したものでもある。ぜひ対峙してほしい。
演劇の街・下北沢などとはまた違う、芸能の街で。夏の風に吹かれて。
text:折田侑駿